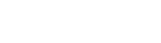【独占取材】辞めキャリア官僚からeスポーツ地方創生へ── 若き副市長が挑む「新潟県三条市」の改造とは
eスポーツ専門の求人メディア「eek(イーク)」では、eスポーツに関するさまざまな仕事にフォーカスした記事をお届けします。第11回目は、新潟県三条市副市長の上田泰成さんです。
33歳の若さで副市長に就任後、前職の経済産業省での経験を活かし、「アウトドアのまち」として知られる三条市でeスポーツを活用した地域活性化に取り組んでいます。
今回は、高齢者向けeスポーツ教室の開催や企業との連携など、地方自治体ならではの視点からeスポーツの可能性を広げる取り組みなどについて伺いました。
33歳の若さで副市長に就任後、前職の経済産業省での経験を活かし、「アウトドアのまち」として知られる三条市でeスポーツを活用した地域活性化に取り組んでいます。
今回は、高齢者向けeスポーツ教室の開催や企業との連携など、地方自治体ならではの視点からeスポーツの可能性を広げる取り組みなどについて伺いました。
国家公務員から地方自治体の副市長へ
──まずは、上田さんのキャリアについてお聞かせください。
私は平成26年に文部科学省に入省し、4年ほど教育行政に携わった後、経済産業省で5年ほど勤務しました。そして2023年4月に三条市の副市長に就任し、現在2年目を迎えています。
実は大阪府出身で、新潟県の出身ではありませんが、市長が国から若い人材を求めていたことがきっかけで、副市長として招かれました。組織の活性化や新しい視点での取り組みを期待されたのだと思います。
──上田さんが副市長を務める、新潟県三条市の特色についても教えてください。
三条市は「アウトドアの聖地」と「ものづくりの街」という二つの顔を持っています。元ゴルフ場を活用した「スノーピークHEADQUARTERSキャンプフィールド」があり、施設には国内外から多くのアウトドア愛好家が訪れます。東京から新幹線で約1時間40分という好アクセスも魅力です。
一方、長い歴史を持つものづくりの伝統も健在で、車のパーツから食器、ナイフ、お箸まで、多様な製品を生み出す職人技が息づいています。中小企業や零細企業が集積し、社長の数が約5000人と「日本一社長が多い街」とも言われています。
近年は年間50億円ものふるさと納税を集める実績も上げており、その返礼品の約半分がアウトドア用品というのも特徴的です。コロナ禍でのソロキャンプブームがこの成長を後押ししました。
行政面では、市長39歳、副市長33歳という若いリーダー陣で運営されており、全国的にも珍しい30代のツートップが子育て支援や教育分野に力を入れています。少子高齢化に対応した学校統廃合など、地元から反発もある困難な決断にも積極的に取り組んでいます。
「ものづくりのまち」とeスポーツの融合
──製造業が中心の街でeスポーツを推進するのは意外に思えますが、どのようなきっかけで始まったのでしょうか?
私が経済産業省時代に日本eスポーツ連合(JeSU)と連携してサウジアラビアとの国際交流に関わった経験があり、eスポーツの可能性を実感していたためです。ただ、面白いことに私自身はほとんどゲームをプレイしません。「eスポーツの推進者なのにゲームをしないの?」と驚かれることが多いですが、ゲームの価値や社会的意義を理解し、それをどう活用するかという視点で取り組んでいます。
最初は苦労しましたが、eスポーツを押し付けないことがとても大事だと考えていました。
そのため、地域企業が抱える課題にフィットする形でアプローチしています。例えば、ものづくり企業は若い世代へのアプローチが難しいという課題を抱えています。製造業はいわゆる「3K」と言われるマイナスな職場環境のイメージがあり、Z世代の若者にアピールする手段として、eスポーツが有効なのではないかと考えたんです。
Z世代にアプローチできる媒体は基本的にSNSかゲーム、この2つしかありません。そこで、eスポーツという媒体を通じて、ものづくりの楽しさを伝えられれば、今までアプローチできなかった若い世代に対して新しい接点を作れると考えました。
高齢者の「若者と触れ合いたい」ニーズをeスポーツで満たす
──eスポーツに関して、上の世代から反発が起こることも少なくないかと思います。そういった層へのアプローチとして、具体的にどのような取り組みをされているのでしょうか。
三条市では、主に高齢者向けのeスポーツ教室を開催しています。NPO法人と連携して、高齢者の方々がゲームを通じて若い世代と交流できる場を創出しています。面白いのは、高齢者の方々の参加動機です。ゲームをすること自体が目的ではなく、「若者と触れ合いたい」という思いが強いんです。お孫さん世代との交流を求めている方が多く、ゲームはあくまでそのためのきっかけになっています。
最近では、地元の大学生や高校生もスタッフとして参加してくれるようになり、世代間交流がより活性化しています。高齢者の方々は若い人たちと会話できるだけで嬉しくなりますし、それが認知症予防やフレイル(虚弱)予防にも繋がっています。例えば、太鼓の達人などのゲームを継続的にプレイすると、脳の前頭葉が活性化されるという医学的なエビデンスもあります。
また、ゲームを通じた交流から、スマートフォンの使い方を教えてもらうなど、デジタルデバイド(高齢者のデジタル格差)を埋める効果も出てきています。上から目線でスマホ教室を開くのではなく、自然な形で若者に質問できる関係性ができているのは大きな成果です。
──他にeスポーツの展開に関して、成果が出ている取り組みはありますか。
BSN新潟放送さんがeスポーツに興味を持ってくださり、来年度に高齢者eスポーツ大会を支援していただけることになりました。会場提供などの協力をいただき、メディアを通じて三条市の取り組みを発信していく予定です。
また、県内の他自治体との交流試合も企画しています。例えば、三条市には有名な温泉施設があるので、他の自治体から来ていただいて、温泉に入った後にeスポーツ交流戦をするなど、観光振興にも繋げる取り組みを進めています。半年に1回程度の定期開催を目指して、相互交流によって地域間の経済効果も生み出そうとしています。
地味で泥臭い取り組みが多いですが、着実に広がりを見せています。現在は役所のスタッフとNPO法人の方々を合わせて20人弱の体制で運営していますが、大学生や高校生の協力も得られるようになり、マンパワーが増えてきています。
──eスポーツに関して、上の世代から反発が起こることも少なくないかと思います。そういった層へのアプローチとして、具体的にどのような取り組みをされているのでしょうか。
三条市では、主に高齢者向けのeスポーツ教室を開催しています。NPO法人と連携して、高齢者の方々がゲームを通じて若い世代と交流できる場を創出しています。面白いのは、高齢者の方々の参加動機です。ゲームをすること自体が目的ではなく、「若者と触れ合いたい」という思いが強いんです。お孫さん世代との交流を求めている方が多く、ゲームはあくまでそのためのきっかけになっています。
最近では、地元の大学生や高校生もスタッフとして参加してくれるようになり、世代間交流がより活性化しています。高齢者の方々は若い人たちと会話できるだけで嬉しくなりますし、それが認知症予防やフレイル(虚弱)予防にも繋がっています。例えば、太鼓の達人などのゲームを継続的にプレイすると、脳の前頭葉が活性化されるという医学的なエビデンスもあります。
また、ゲームを通じた交流から、スマートフォンの使い方を教えてもらうなど、デジタルデバイド(高齢者のデジタル格差)を埋める効果も出てきています。上から目線でスマホ教室を開くのではなく、自然な形で若者に質問できる関係性ができているのは大きな成果です。
──他にeスポーツの展開に関して、成果が出ている取り組みはありますか。
BSN新潟放送さんがeスポーツに興味を持ってくださり、来年度に高齢者eスポーツ大会を支援していただけることになりました。会場提供などの協力をいただき、メディアを通じて三条市の取り組みを発信していく予定です。
また、県内の他自治体との交流試合も企画しています。例えば、三条市には有名な温泉施設があるので、他の自治体から来ていただいて、温泉に入った後にeスポーツ交流戦をするなど、観光振興にも繋げる取り組みを進めています。半年に1回程度の定期開催を目指して、相互交流によって地域間の経済効果も生み出そうとしています。
地味で泥臭い取り組みが多いですが、着実に広がりを見せています。現在は役所のスタッフとNPO法人の方々を合わせて20人弱の体制で運営していますが、大学生や高校生の協力も得られるようになり、マンパワーが増えてきています。
eスポーツを「広める」だけでなく「地域の課題解決に繋げる」
──行政の立場からeスポーツを推進する上での課題は何ですか。
最大の課題は「どうやって、eスポーツを地域の課題解決に繋げるか」です。単にeスポーツを広めるだけでなく三条市では、単にeスポーツを広めるだけでなく、認知症予防や介護予防、教育、デジタルデバイドの解消など、具体的な社会課題とeスポーツを結びつける取り組みを進めています。
もう一つの課題は、eスポーツに参画する企業が少ないという点です。日本は課題先進国であり、地方が抱える社会課題を解決するビジネスモデルを確立できれば、それを海外に輸出できる可能性もあります。eスポーツを活用した介護予防やフレイル予防のパッケージを開発し、将来的にグローバル展開も視野に入れています。
また、行政サービス全般に言えることですが、これまでの供給者目線から利用者目線への転換も重要です。eスポーツも押し付けるのではなく、住民や企業のニーズに合わせた形で展開することで、より効果的な取り組みができると考えています。
──庁内での取り組みについても教えてください。
eスポーツを通じて役所の組織活性化にも取り組んでいます。例えば、去年の4月に入庁した新入職員を対象に「ぷよぷよ」のeスポーツ大会を開催しました。市長と私もエキシビションマッチで参加し、ピザやジュースなども用意して交流を深めました。
この取り組みの良かったところは、部署の垣根を超えて横のつながりができたことです。最初はスポーツ担当部署が運営していましたが、今は人事課の福利厚生の一環として定着しています。私がいなくなっても継続される仕組みができたのは大きな成果だと思っています。
また、地元メディアに取り上げられることで職員のモチベーションが上がるという効果もあります。三条市には「三条新聞」という地元紙があり、そこにeスポーツの記事が掲載されると職員の間で話題になり、士気が高まります。地方では特に紙媒体の影響力が大きく、メディアとの連携は重要です。
eスポーツを押し付けるのではなく、地域や組織が抱える課題に合わせたアプローチを考える
──eスポーツを通じた地域活性化や社会課題解決に関心を持つ人へのアドバイスをお願いします。
eスポーツはただのゲームではなく、さまざまな可能性を秘めたツールです。介護予防、教育、観光振興、デジタルデバイドの解消など、用途は無限にあります。大切なのは「何のために」という目的意識と、継続して取り組む姿勢です。
特に地方自治体や企業がeスポーツに取り組む際には、押し付けるのではなく、地域や組織が抱える課題に合わせたアプローチを考えることが重要です。システム化して続けられる仕組みを作り、小さな成果を積み重ねていくことで、徐々に理解者や協力者が増えていきます。
私たちの取り組みはまだ始まったばかりですが、高齢者と若者の交流やデジタルデバイドの解消など、着実に成果が出始めています。これからのeスポーツは、より多様な形で社会に浸透していくでしょう。その可能性を一緒に広げていければと思います。
──上田副市長、ありがとうございました!
取材・文:小川翔太
新着の記事
- ALGS札幌はアップデートできるのか──「3年連続の札幌開催が決定」Electronic Arts Esports 総合責任者 モニカ・ディンスモア【特別インタビュー】
- まずeスポーツを知ってもらうことから──市町村「33か所」と向き合う、神奈川県福祉子どもみらい局 福祉部 高齢福祉課【インタビュー】
- なぜ10年以上「eスポーツ」に関わる望月伸彦氏と筧誠一郎氏が、いま委員会を立ち上げたのか【埼玉eスポーツ推進委員会】
- eスポーツデバイスの企業に「どんな方と一緒に働きたいか」を聞いてみた【ゲーミングバザー2025編】
- テレ東・藤平氏が挑む「eスポーツの大衆化」──鍵となるのは「ゴルフ・水泳」の演出
- 【インタビュー】しーにゃさんって何者? 海外eスポーツチームで活躍する日本人コンテンツクリエイターの仕事
- eスポーツチームのスタッフってどんな仕事?
- モータースポーツがeスポーツとコラボした理由とは──株式会社日本レースプロモーション 代表取締役社長 上野禎久氏
- 小さな情報でも「集める」と価値が出る──eスポーツライター・Yossyさん
- メディア初登場!「QT DIG∞」第五人格のメンバー全員にインタビューしたら元気すぎた