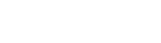eスポーツ採用の国際大会「第20回アジア競技大会」のキーマン、JeSU愛知支部 片桐代表理事を直撃インタビュー
普段は表に出てこない「eスポーツを盛り上げる裏方さん」にインタビューする本連載。
今回は、ついに日本eスポーツ連合(JeSU)愛知県支部 代表理事の片桐氏(ASIA esports EXPO 2025 実行委員長)が登場。
・2026年開催の「第20回アジア競技大会」(愛知・名古屋)について
・採用されたeスポーツタイトルについて
・これからのeスポーツ界には何が必要なのか
「ASIA esports EXPO 2025」の控室で、緊張感のあるインタビューとなりました。
今回は、ついに日本eスポーツ連合(JeSU)愛知県支部 代表理事の片桐氏(ASIA esports EXPO 2025 実行委員長)が登場。
・2026年開催の「第20回アジア競技大会」(愛知・名古屋)について
・採用されたeスポーツタイトルについて
・これからのeスポーツ界には何が必要なのか
「ASIA esports EXPO 2025」の控室で、緊張感のあるインタビューとなりました。
eスポーツ界のヒーローを生み出し、親世代の「考え」を変える
──本日はよろしくお願いいたします。今回の「ASIA esports EXPO 2025」をはじめとして、現在の愛知県はeスポーツに力を入れているかと思います。愛知県のeスポーツの座組にはどのような強みがあるのでしょうか。
愛知県のeスポーツの強みは、地域の中核を担う「企業」と「メディア」が本気で参画していることです。中日新聞様、CBCテレビ様、中部テレコミュニケーション様など、社会的責任を持ったパートナーが一丸となって動いていることが、他県にはない「厚み」だと感じています。
──ついに開催となった「ASIA esports EXPO 2025」について、こだわりのポイントを教えてください。
「ASIA esports EXPO 2025」は、2026年に名古屋で開催されるアジア競技大会の「プレプレ大会」として、本番を見据えた試金石となる大会と位置付けています。
今回は、単なるイベントに終わらせず、国際色や教育的意義も重視しています。例えば海外から選手を招致したり、高校生に大会運営に参加してもらったりなど、全世代・全方位にアプローチする設計を意識しました。
「ASIA esports EXPO」
メインステージ
──私たちも会場を見させていただき、とても幅広い世代が足を運んでいる印象を受けました。特に『ポケモンユナイト』のイベントは大盛況でしたね。しかし、「目の前のお客さんに楽しんでもらう」という短期的な達成だけでなく、片桐委員長は立場上、長期的な目線でeスポーツのことを見ているかと思います。eスポーツが持つ可能性について、どのように捉えていますか?
「eスポーツこそが次の時代のスポーツである」と捉えています。
私は長い間、伝統的なフィジカルスポーツのビジネスの世界に身を置いてきました。具体的にはプロ野球やプロサッカー、また、プロサッカークラブのサッカー以外の競技、例えばパルクールなどに関わってきました。
その経験から、eスポーツが(フィジカルスポーツと同様に)「遊び」と「学び」の境界を越え、次世代を育てる手段になると確信しています。
いま多くの若者がeスポーツに熱狂していますが、彼らの前に立ちはだかるのは、「親世代からの“ストップ”」です。
(親世代からの)「ゲームばかりしていないで」という声が、若者の挑戦を断念させてしまう。これは非常にもったいないことです。だからこそ、我々、大人たちの考え方を変えなければなりません。
「eスポーツが承認され、応援される文化」をつくる必要があるのです。
それを後押しするのが、大会や国際イベントでの「ヒーローの誕生」だと考えます。
2026年開催の「第20回アジア競技大会」で、日本人選手が多くのメダルを獲れば、世代を超えた理解や共感が生まれるきっかけになるでしょう。
子どもの“遊び”を大人が“教育”に昇華する──繰り返されるスポーツ誕生の歴史
──なぜeスポーツは、ここまで若者たちの心を掴むのだとお考えですか。
「やらされる」のではなく「やってしまう」のが、eスポーツの最大の魅力だと思っています。
かつての子どもたちにとっての「やってしまう」遊びが、キャッチボールやバットの素振りだったのに対して、今の子どもたちの「やってしまう」遊びが、eスポーツに置き換わって来ているのです。
子どもたちは、親が何と言おうと夢中になってしまうほどゲームに没頭します。それが、まさにeスポーツの持つ圧倒的な「引力」です。
私自身、6歳の息子を育てているのですが、野球やサッカーは「やりなさい」と言わないとやってくれないのに、ゲームだけは「やめなさい」と言ってもやり続けるんです。
フィジカルスポーツの成り立ちの歴史がそうであったように、子どもたちの自然な熱量に、大人たちが「社会的なルール」や「意味づけ」を加えることで、教育的な価値が生まれるのです。
私は大学生時代に学んだ「スポーツとは、子どもの“遊び”に、大人がルールを加えることで、社会性を育てる仕組みである」という考え方に、今も強く共感しています。
eスポーツは、フィジカルスポーツが抱える課題を解決する、非常に強力なコンテンツであり、「”遊び”の力を活かした社会接続の可能性」を持っていると感じています。
──かつてフィジカルスポーツが辿った歴史を、eスポーツが辿ろうとしているのですね。eスポーツと教育との連携について、愛知県で行なっている取り組みについて教えてください。
県内の高校と連携して授業プログラムを実施しています。今回の「ASIA esports EXPO 2025」でも、地元高校の生徒たちが授業の一環として大会運営に参加してくれました。
まさに、eスポーツの文脈で「現場で学び、社会とつながる」経験を提供することができています。
さらに、大学生リーグと大規模大会を連動させる設計も行っており、リーグで勝ち上がった学生が本大会のステージに立てる仕組みも整えつつあります。教育と大会、地域をつなぐ設計を意識しています。
こうした動きはフィジカルスポーツの業界でも進んでいます。例えば、筑波大学では、あらゆる大学生スポーツを一括でブランディング・配信する仕組みを整備しています。そのプロジェクトに注視しており、eスポーツにも同様の仕組みを根づかせていくことが重要だと感じています。
今後の愛知県の取り組みとしては、eスポーツを「自己表現」や「学び」、「キャリア形成」の場として活用していきたいと考えています。
そのためには、教育・メディア・ビジネスを横断する人材育成の仕組みを、さらに整えていくことが必要です。
eスポーツ大会に賞金は必要なのか──「一度の賞金」ではなく「一生の名誉」を手にして欲しい
──今回の「ASIA esports EXPO 2025」は、アジア競技大会に向けた「プレプレ大会」ということですが、具体的にはどういった位置付けや狙いがあったのでしょうか?
「ASIA esports EXPO 2025」は、2026年アジア競技大会に向けた「本気の準備」となるイベントです。
来年にはプレ大会、その半年後には本番となる「2026年アジア競技大会」が控えています。私たち運営側はもちろんですが、選手にとっては全ての大会が勝負の場なので、私たちもスタンスとしては「準備」という気持ちは微塵もなく、関わるスタッフみんなが人生をかけて臨んでいます。
今回の大会では「2026年アジア競技大会」で実装する予定の、舞台装置を取り入れ、できる限り再現度を高めました。また、海外選手の招致や日本人選手との混合試合、観客動員を通じて「世界大会の臨場感」を体感できる設計になっています。
「ACTORS☆LEAGUE」の俳優の皆様の協力による集客も含め、幅広い客層に多角的に「本気の競技」としてのeスポーツを伝える場になったと感じています。
「ASIA esports EXPO 2025」内で名古屋ストリートファイター6
対戦会「鯱拳」も同時開催された
──アジア競技大会では、一般的なeスポーツの大会とは異なり賞金が出るわけではありませんが、選手たちが出場する意義についてどのようにお考えですか。
確かに、アジア競技大会は一般的なeスポーツ大会のように高額な賞金が出るわけではなく、名誉や社会的な評価を与える大会です。
しかし、フィジカルスポーツの世界では、大会で得られる賞金よりも、その後に得られるスポンサー契約や情報発信力のほうが、(金銭的にも)はるかに大きな影響力を持ちます。
私は、これまでにプロ野球やJリーグ、パルクールといったさまざまな競技の選手たちと関わってきました。どの世界でも本質的に問われているのは、「競技を通じて、どうすれば誇りを持って生きていけるのか」です。
eスポーツもまったく同じで、1回の勝利や賞金ではなく、どれだけ多くの人を惹きつけ、支持される存在になれるかが問われています。
その意味で、アジア大会での活躍が、若い世代にとって「eスポーツを通じた生き方もある」という新しい選択肢になることを、私は心から期待しています。
eスポーツを「文化」に──遊びでは終わらせない
──少し踏み込んだ質問をさせてください。昨今、若年層はアジア競技大会やオリンピックなどの、国際大会に興味を持っていない印象があります。eスポーツに限らず、スポーツ全体が抱える課題なのかもしれませんが、若年層を巻き込む取り組みについてはどのようにお考えですか。
今後のスポーツは「リアルに集客すること」よりも、どれだけ「視聴者の可処分時間に入り込めるか」が重要だと考えています。
実際に、プロ野球やプロサッカーの収益は、入場料よりもスポンサーシップや配信収益が大きな比重を占めています。スポーツビジネスの中核はすでに「顧客との接点をどう生むか」というデジタル戦略に移っているのです。
若者にとっての「スクリーン」は、すでにテレビではなくスマホであり、将来的にはARグラスや音声デバイスになっていくでしょう。
eスポーツはその文脈に完全にフィットしており、新しい視聴体験やファン形成のフロントランナーになる可能性を秘めていると考えています。
──お話を伺っていると(フィジカルスポーツにはできない)「eスポーツだからこそできる施策」も出てくるように感じて、とても楽しみになってきました。最後になりますが、今後の展望と、愛知県でのeスポーツの可能性について教えてください。
愛知県には、ものづくりやスポーツ文化、教育資源などを融合できる土壌があります。そして、今の若い世代には、eスポーツを通じて「好きなことで社会とつながる」という新しい生き方を選ぶ力があると信じています。
私たちは、「eスポーツが子どもたちをダメにする」ではなく、「eスポーツが子どもたちを育てる」社会をつくりたいと思っています。そのために、教育現場との連携や、高校・大学での人材育成、そして地域の多世代交流を通じて、eスポーツが“文化”として根づく未来を描いています。
愛知でのこの取り組みが、全国やアジアに広がっていくよう、引き続き挑戦していきたいと考えています。
──JeSU 愛知支部 代表理事・片桐様、ありがとうございました!
取材・文:小川翔太、松永華佳
新着の記事
- ALGS札幌はアップデートできるのか──「3年連続の札幌開催が決定」Electronic Arts Esports 総合責任者 モニカ・ディンスモア【特別インタビュー】
- まずeスポーツを知ってもらうことから──市町村「33か所」と向き合う、神奈川県福祉子どもみらい局 福祉部 高齢福祉課【インタビュー】
- なぜ10年以上「eスポーツ」に関わる望月伸彦氏と筧誠一郎氏が、いま委員会を立ち上げたのか【埼玉eスポーツ推進委員会】
- eスポーツデバイスの企業に「どんな方と一緒に働きたいか」を聞いてみた【ゲーミングバザー2025編】
- テレ東・藤平氏が挑む「eスポーツの大衆化」──鍵となるのは「ゴルフ・水泳」の演出
- 【インタビュー】しーにゃさんって何者? 海外eスポーツチームで活躍する日本人コンテンツクリエイターの仕事
- eスポーツチームのスタッフってどんな仕事?
- モータースポーツがeスポーツとコラボした理由とは──株式会社日本レースプロモーション 代表取締役社長 上野禎久氏
- 小さな情報でも「集める」と価値が出る──eスポーツライター・Yossyさん
- メディア初登場!「QT DIG∞」第五人格のメンバー全員にインタビューしたら元気すぎた