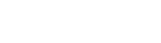【ENZAさんインタビュー#3】経験の差に苦しむ日本チーム……チームづくりに“世界一の企業”を目指すマインドを
eスポーツ専門の求人メディア「eek(イーク)」では、eスポーツに関するさまざまな仕事にフォーカスした記事をお届けします。今回は、複数のeスポーツチームでゼネラルマネージャー(以下、GM)を務めてきた、ENZAさんへのインタビューです。
本企画では、ENZAさんに複数のテーマにわたってお話を伺っています。#3のテーマは、eスポーツチームにおけるチームづくりについて。勝利を目指すにあたってチーム運営が持つ影響力にフォーカスし、海外トップチームとの比較などから、日本チームが抱える課題や難しさについて聞きました。
過去の記事:
【ENZAさんインタビュー#1】eスポーツチームを“勝たせる”ゼネラルマネージャー(GM)の仕事とは?
【ENZAさんインタビュー#2】ゲーム理解度の差を埋め、日本のeスポーツチームが世界で勝つために必要なもの
本企画では、ENZAさんに複数のテーマにわたってお話を伺っています。#3のテーマは、eスポーツチームにおけるチームづくりについて。勝利を目指すにあたってチーム運営が持つ影響力にフォーカスし、海外トップチームとの比較などから、日本チームが抱える課題や難しさについて聞きました。
過去の記事:
【ENZAさんインタビュー#1】eスポーツチームを“勝たせる”ゼネラルマネージャー(GM)の仕事とは?
【ENZAさんインタビュー#2】ゲーム理解度の差を埋め、日本のeスポーツチームが世界で勝つために必要なもの
海外チームと日本チームにおける選手獲得の進め方の違い
――#1でお話いただいた内容に、GMが携わる仕事の1つである選手獲得の話題がありました。海外チームと日本チームで、選手獲得の進め方に違いはあるのでしょうか?
ENZA:
日本のチームでは、欲しい選手のリストをつくるときに、今いる選手にどのような選手が欲しいのか聞くことが多いです。たいていチームには核となる選手がいて、その選手が欲しいメンバーを集めてあげるのが、今の主流だと思います。海外のチームだと、チーム側が欲しい選手の候補を持っていて、交渉して獲得できなかったら次の選手に当たるという感じで、チーム主体で進めることが多いと思います。
――選手を適切に評価できる人がチームにいたら、海外チームの進め方のほうが理想的だと思いますか?
ENZA:
ただ選手の仲がいいからとか、そういう理由だけで選ぶのは、もちろん良くありません。でも、主観だけでなく、しっかりと統計データやスタッツなどの第三者視点の情報も踏まえて考えられているなら、選手主体で集めるのも問題ないと思います。やはり性格などパーソナルな部分は、選手のほうがよく知っていることが多いので。――合う合わないといった相性的な部分でしょうか?
ENZA:
それもそうですし、信頼できる選手であるかどうかも大事ですね。 素行が良くないとか、そういうことが後で発覚するのを防ぎやすくなります。国内外のチームで、上手い選手を取ったものの、チームにフィットしないからメンバーを変更するなど、そういう部分で上手くいかないチームは多いですね。――それぞれメリットとデメリットがあって、どちらのやり方がいいというわけではないと。
ENZA:
そうですね。選手の合う合わないがあるのは、海外も日本も同じなので。勝利を目指すうえで、チーム運営が持つ影響力とは?
――『レインボーシックスシージ』(以下、R6S)では、ブラジルチームの「w7m esports」が2024年の世界大会で優勝したのち、選手5名が全員変わったにも関わらず、再びメジャー大会で優勝を果たした例があります。チーム運営側の力が結果に大きく影響を与えているように見えますが、これはなぜ実現できたと思われますか?
ENZA:
実際の内情を知っているわけではなく、かつ最近『R6S』のシーンを追えていないのであくまで客観的な考えですが、これはそもそも『R6S』がブラジルでとても人気が高く、レベルの高いメジャー地域であることが大きく影響していると思います。メンバーが入れ替わったとしても、ブラジルというメジャー地域のトップ選手を迎え入れている時点で、かなりのアドバンテージがあります。レベルの高いブラジルで勝つこと自体が難しいので、そこで勝ち上がるほど強いチームが、世界大会で優勝したということかなと。『League of Legends』(以下、LoL)で言えば、韓国のトップ選手を集めたら強いチームができるのと同じですね。
――背景にある、地域的なレベルの高さや選手層の厚さが大きいということですね。
ENZA:
加えて、先ほどの「w7m esports」というチームに関して言うと、『R6S』部門に注力しているチームのように見えます。大手チームになるほど、幅広い部門を持つことによって、その分良くも悪くも広く浅くなりがちです。部門が多すぎると、どうしてもチームの上の人たちも全部を見るのが難しくなってくるんですね。なので、一部のタイトルに特化したチームほど、そのタイトルで勝ちやすい傾向があるかもしれません。昔は、一部のタイトルで世界大会優勝まで行った後に、別の部門に広げていく形が主流だったんです。得たノウハウを使って、別のタイトルにも展開していくやり方ですね。
――世界大会での優勝経験がある場合、選手以外の、チーム運営側が持つノウハウとはどのようなものがあるのでしょうか?
ENZA:
マネジメントに関して成功体験があるので、そのやり方をそのまま流用できます。eスポーツに限った話ではありませんが、やって上手くいったものを取り入れていく。優勝経験があれば、その経験から上手くいったものが何かという判断ができます。世界大会に行ったときも、現地に行ったときに何が必要か、何ができるかは経験がないとわからないことが多いです。例えば、5on5タイトルでは基本的に、自分たちで現地でスクリム相手を探さなければなりません。でも、特にマイナー地域のチームの場合、実績がない限り、強い相手とスクリムするのは難しいんですよ。現地に行ったものの、なかなか練習相手が見つからないまま、スクリムができない状態で本番を迎えることもありえます。
でも、優秀なコーチを雇っていると、コーチ同士の横のつながりがあって、それによって強い地域のチームとスクリムができたりするんですね。そうやって横のつながりをしっかりつくっておかないと、世界大会に行ったときに上手くいかない要因の1つになります。
――選手たちに用意する練習環境の質が変わってくるわけですね。
ENZA:
海外で練習するとなったとき、ゲーミングハウスを経験したことがないチームの場合、みんな慣れていないので、どう生活したらいいかもわからなくなりがちです。でも、チーム運営がちゃんとノウハウを持っていれば、選手が求めているものをスムーズに用意することができます。例えば、世界大会のときにご飯が合わない経験をしたことがある人たちは、コンディションを維持するために、レトルトのご飯などを期間分持っていきます。選手がゲーム以外のことを考えると弱くなるという話(#1参照)をしましたが、これも同じことですね。
選手がストレスを感じることがあれば、その分練習の質が悪くなる可能性があるので、そこはチーム運営側の力が表れるところ。強いチームが結果を出し続けるのは、経験によるノウハウがあるからという理由が大きいです。
――日本チームにとっては、チーム自体が世界大会出場などの経験をより積んでいく必要があると。
ENZA:
ですが、現状は世界大会を経験できるチーム数がかなり限られています。国内大会で優勝した1チームが世界大会に行けるとしたら、その1チームしか経験を得られない。それ以外のチームが試行錯誤するには、ノウハウを持った人を採る必要がありますが、日本ではチーム間での人材の入れ替えがあまり起きていません。一般企業でも、いろいろな人材が行ったり来たりすることで、その人の持つノウハウが活かされるというメリットがありますよね。“調べても出てこないけれど、そこで働いていた人は知っていること”というのは多々あります。チームは企業としても強くなるべきで、そうした部分は課題になっているように思います。
ただ、そもそも世界大会の出場枠には、その地域の強さが最も関係していて、弱い地域は枠が少なくなります。強い地域だったらより多く枠がもらえて、それだけ多くのチームが経験が得られるわけですから、それを目指さなければなりません。地域として強くなろうとするには、やはり選手を育てて強くする必要があるので、育成が重要だというのが自分の考えです。
経験や基礎の差が、日本チームにとっての難しさに
――チームの完成度を上げていくフェーズにおいても、海外チームに比べて日本チームは時間がかかる印象があります。これもチームの経験の差が影響しているのでしょうか?
ENZA:
チームのノウハウの少なさから、マネジメントの仕方に困ってしまって、人間関係やマインドをつくっていく部分で苦労することがあると思います。例えば、大会のためにみんなで一緒に生活しながら練習するようになったけれど、初めてだから人間関係やコミュニケーションの部分で上手くいかないとか。そういうゲーム外の問題が発生する場合があって、それも課題になります。あとは、やはり選手たちの基礎の違いですね。大会が始まると、勝つためには戦術や戦略を学ぶ必要がありますが、基礎が足りないと基礎も学ばなければなりません。そうすると、選手にとっては学ぶことが多くなりすぎて、とても難しいんですね。すでに基礎ができている海外トップチームの場合は、戦術や戦略の話だけすればいいということになります。
――#2でも基礎の話題が挙がりましたが、それくらい重要だということですね。
ENZA:
基礎は本当に重要で、かつ一番最後に行き着くところなんですよ。戦術や戦略ができている選手がどこで差がつくのかというと、基礎の部分で最も差がつきます。基礎はいきなり上手くならないので、ものすごく時間かかるんですよね。試合中に10のことしか考えていなかった選手が、知識を持っている選手のように100のことを考えろと言われても、いきなりそんなことはできません。でも、トップの競技シーンでは100のことを考えなければならず、そこまでキャパシティを広げるのがすごく大変なんです。
FPSゲームのトップ選手なら、エイム力はみんなあって当然で、それほど大きな差はありません。では、いったい何で差がつくのかということですが、試合中には考えるべきことに対するリソースの配分があります。エイムだけが強い選手もいると話しましたが(#1参照)、それはエイムにほとんどのリソースを割いているからです。その選手が、プラスで90のことを考えなければならなくなると、エイムが弱くなります。
国内大会では強かったのに、国際大会ではパフォーマンスが悪くなったように見える選手がいるのは、そういった課題に取り組んでいる最中だからという場合も多いと思います。
――日本チームが苦労している基礎というのは、例えばどういったものなのでしょうか?
ENZA:
競技シーンの基礎にはあらゆるものが含まれますが、例えばチームゲームにおいては、試合において何を言うか、何を言わないかというコミュニケーションのルールがあります。試合のなかで、「こういう状況では、これを必ず行う」と決まっているものがあるんですね。その過程を経て初めて、コミュニケーションを取らなくてもその動きができる、阿吽の呼吸が生まれます。『Counter-Strike』での話を例に挙げたように(#2参照)、海外では経験を持っている選手やコーチがいろんなチームに行って、そういうルールを“やって当たり前”のものとして教えています。若い選手たちがそれを基礎として学んで、今の競技シーンのレベルがあるんです。
なので、まだ歴史の浅いタイトルでは状況が違います。例えばモバイルゲームで、日本チームが世界で戦えているのには、そういう背景があると思います。ただ、長年積み重ねられてきたものがあるタイトルやジャンルでは、未開拓なところからやっている日本はどうしても難しくなります。
チーム運営の話も同じですね。経験があるチームは、世界大会に行ったときに「選手たちをこうサポートすべき」という当たり前があるんです。そういう点で、日本は急激に盛り上がった地域の宿命というべきか、積み重ねてきたものが少ないから苦労しているのだと思います。
チームも「世界一の企業になる」というマインドが必要
――それでは最後に、世界で勝てるチームをつくるために日本のeスポーツチーム運営に何が必要だと感じるかを、改めて教えてください。
ENZA:
チームとして企業も選手も一丸となって、勝つために取り組んでいかないといけないと思います。選手たちだけが頑張っていても勝つことはできないし、チーム側も企業としてより強くなる方法を考えていくべきです。チームの人たち全員が「世界一の企業になるんだ」という、それくらいのマインドを持つ必要があります。組織として妥協せず、そういう人材を集めるのはすごく難しいことだとは思います。でも、積んできた経験が少ない後進国の日本が、世界のチームたちに勝とうとするなら、やはり一丸となって取り組んでいかなければならないと思います。
――ENZAさん、ありがとうございました!
取材・文:綾本ゆかり
新着の記事
- なぜ10年以上「eスポーツ」に関わる望月伸彦氏と筧誠一郎氏が、いま委員会を立ち上げたのか【埼玉eスポーツ推進委員会】
- eスポーツデバイスの企業に「どんな方と一緒に働きたいか」を聞いてみた【ゲーミングバザー2025編】
- テレ東・藤平氏が挑む「eスポーツの大衆化」──鍵となるのは「ゴルフ・水泳」の演出
- 【インタビュー】しーにゃさんって何者? 海外eスポーツチームで活躍する日本人コンテンツクリエイターの仕事
- eスポーツチームのスタッフってどんな仕事?
- モータースポーツがeスポーツとコラボした理由とは──株式会社日本レースプロモーション 代表取締役社長 上野禎久氏
- 小さな情報でも「集める」と価値が出る──eスポーツライター・Yossyさん
- メディア初登場!「QT DIG∞」第五人格のメンバー全員にインタビューしたら元気すぎた
- ZETA千葉さんも登壇── eスポーツ・ゲームコミュニティのこれからを考える
- なぜドリエルは「プロゲーマーの"不健康"なイメージ」に着目できたのか?