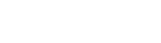eモータースポーツ業界の先駆者 ──北浦代表にインタビュー【NGM株式会社】
普段は表に出てこない「eスポーツを盛り上げる裏方さん」にインタビューする本連載。
今回は、「日本で最もゲームをプレイしないeスポーツ会社の社長」というユニークな肩書を持つ、NGM株式会社の北浦諭氏を取材しました。
北浦氏は『グランツーリスモ』の大会で選手に賞金が出せるよう、認定ドライバーの制度作りに尽力し、国内唯一の賞金制大会「AUTOBACS JEGT GRAND PRIX」の立ち上げた、まさに「eモータースポーツ業界の先駆者」といえるキーマンです。
今回は、「日本で最もゲームをプレイしないeスポーツ会社の社長」というユニークな肩書を持つ、NGM株式会社の北浦諭氏を取材しました。
北浦氏は『グランツーリスモ』の大会で選手に賞金が出せるよう、認定ドライバーの制度作りに尽力し、国内唯一の賞金制大会「AUTOBACS JEGT GRAND PRIX」の立ち上げた、まさに「eモータースポーツ業界の先駆者」といえるキーマンです。
きっかけは「どぐら選手」&「たぬかな選手」 ── なぜ「ゲームをしない社長」がeスポーツ会社を立ち上げたのか
──NGM株式会社の設立に至った背景を教えてください。
NGM株式会社を設立したのは、私の強みである「イベントプロデューサーとしての経験」がeスポーツの分野で活かせると感じたからです。
私は神戸を拠点に活動しており、(別会社として)父から継いだイベント制作会社も経営しています。その会社で地元のお祭りや国際交流イベント、スポーツ大会など、地域の様々なイベント制作に携わる中で、新しい事業を作りたいと考えるようになりました。
丁度、そのタイミング(2018年頃)にeスポーツ関連の報道を見るようになり、eスポーツに興味を持ち始めました。自分自身はゲームをプレイしないのですが、イベントプロデューサーとして何かできるのではと思い、会社設立に踏み切ったのです。
──具体的にどのような番組(報道)を御覧になったのでしょうか。
大阪にあるCAG OSAKA(旧:CYCLOPS athlete gaming)を取材した番組を見たことが、eスポーツ業界に興味を持ち始めたきっかけです。
当時、所属していたプロゲーマーである、どぐら選手とたぬかな選手がメインで取り上げられており、特徴的な名前であったことや、大阪という身近な場所での活動であったこともあり、興味を持つようになりました。
独自の認定ドライバー制度を作り、賞金を出せる仕組みを構築
──現在、どのようなeスポーツ事業を展開されているのでしょうか。
事業領域としては、eモータースポーツを始めとする、FPSや格闘ゲームなどのイベント企画・制作が主軸となっています。また、NTTグループと連携したeスポーツ施設の運営や、ゲーミングチームのマネジメント事業、eスポーツ機材に特化したレンタル事業、eスポーツを通じたソリューション事業も展開しています。
こうした幅広い事業を通して、私たちはeスポーツのトータルマネジメントカンパニーとして「eスポーツが当たり前になる世の中へ。」をミッションに掲げて活動しています。
──これまで手がけたイベントの中で、特に印象に残っているものを教えてください。
大きなイベントでは、『グランツーリスモ(SPORTおよび7)』で唯一の賞金制大会である、「AUTOBACS JEGT GRAND PRIX」を1から立ち上げたことを挙げたいです。2022年からは、それまでメインスポンサーであったオートバックスセブンさんに主催者となっていただき、現在は運営会社として携わっています。
当時、『グランツーリスモ(SPORTおよび7)』はJeSU(日本eスポーツ連合)のプロライセンス発行タイトルではなかったため、賞金を出すことが難しい状況でした。そこで、トッププレイヤーとしてのスキルの高度性を証明する「JEGT認定ドライバー制度」を独自に作ることで、賞金を出せる仕組みを構築しました。
初年度は2名だった認定ドライバーですが、2025年4月現在では203名にまで増えています。
また、小規模ながら印象に残ったイベントは、NTT西日本(兵庫支店)さんと神戸大学さんとの共同事業で実施した高齢者向けeスポーツ体験です。eスポーツ体験前後の心理的興奮度を比較測定する実証実験で、高齢の方々も『グランツーリスモ』を特に熱心に楽しまれていました。
「eスポーツは年齢や性別、国境、国籍を越えて楽しめるユニバーサルなもの」という言葉が単なる綺麗事ではなく、実現している瞬間を目撃できたことは、私にとって大きな喜びであるとともに、事業の意義を感じられる機会でした。
集客の失敗から得た学び ──「ゲーマーの視点がない大会」は誰も参加したいとは思わない
──イベント運営だけでなく、制度作りにも関わっていたとは驚きです。
そうですね。実はNGMの創業前から、兵庫県の有馬温泉の旅館の専務であり、JeSU兵庫支部の副会長をされていた方との交流があり、その方からeスポーツの詳しい話を聞かせてもらったり、有識者を紹介いただいたことで、実践を積みながら勉強していくことができました。
2019年の国体でeスポーツが初めて採用された際には、『ウイニングイレブン(現:eFootball™)』の兵庫県予選から関わりました。
最初から成功したわけではなく、eスポーツイベント運営の知識がなかったため、選手もお客さんも集まらず、大きな失敗を経験しました。
──失敗経験からどのようなことを学びを得ましたか?
「ゲーマーの方々と接点を持つこと」が重要だと気づきました。ゲーマーの視点がないまま大会を運営しても、誰も参加したいとは思いません。
例えば、野球の大会を開催したとして「運営側は野球に関心がなく、皆さんのことも知りません」と言われたら、誰も参加したいとは思わないですよね。私自身がゲームをプレイしないこともあり、この状況では誰も大会に出たがらないと実感しました。
そこで私が考えたのは、そのゲームを自身もプレイすることよりも、ゲーマーの方々とのコミュニケーションをさらに深めるべき、ということでした。
私たち運営側とゲーマー側では、イベントや大会に対しての向き合い方、考え方は少し異なります。例えばレギュレーションやルールについて、我々は「これでいいだろう」と思っていても、実際にプレイするゲーマー側からは様々な細かい指摘があります。
そういった部分をないがしろにせず、真摯に向き合うことが何より重要なんだと感じ、できるだけコミュニケーションを取ることを心がけました。特に初期の頃はゲーマー側から直接教えを請うことも多くありましたし、もちろん運営側としてこう考えているということもしっかりと伝えて理解を得るようにもしてきました。
大会を成功させるには「運営側の俯瞰的な視点」と「ゲーマー側の没入的な視点」、両方の視点をうまく組み合わせることが最も重要な鍵だと思います。
「あえてゲームをプレイしない理由」── 初心者の目線を忘れないこと
──ちなみにご自身のSNSのプロフィール欄で「日本で最もゲームをプレイしないeスポーツ会社の社長」(2025年4月現在)と記載がありますが、こちらの意図は何でしょうか。一般的にeスポーツ業界では「自分はこんなにゲームをやってます!」というアピールをする経営者が多いので、真逆のブランディングだなと。
私個人の見解ですが、eスポーツ会社を経営するうえで、常に初心者の目線を忘れないことが非常に重要です。
日本eスポーツ白書の予測によると、2025年には国内のeスポーツファン数が1,000万人を超えます。ただし、この数字には熱心なファンだけではなく「好きなゲームであれば少し見る程度」の層も含まれているのではと思っています。同じ基準で考えると、リアルスポーツのファン層は7000万人から8000万人にも達するでしょう。つまり、eスポーツ市場はまだまだ成長段階なのです。
eスポーツは一度体験すればその魅力が伝わりますが、最初のきっかけがなければ多くの人は興味を持ちません。eスポーツの魅力を知らない人はまだ多く存在します。そのため私自身はあえてゲームをプレイせず、常に初心者目線でいることで、eスポーツを知らない人々にどうアプローチすべきかを考え続けています。
──現在のeスポーツイベント全般の課題についてどのようにお考えですか?
最大の課題は「eスポーツ」自体がまだ特別視されていることです。『eFootball™』や『グランツーリスモ』『ストリートファイター』の大会はすべて「eスポーツの大会」と一括りにされますが、野球やサッカーの試合を「スポーツの試合」とは呼びません。
また、ニュース番組では必ず「eスポーツとはビデオゲームを競技化したものの総称」という説明が付くことからも、社会での一般化はまだ進んでいないといえます。
このようにeスポーツへの理解が広まっていない状況では、競技者のニーズを十分に理解していないイベント主催者によって、選手や参加者が置き去りになっているケースが多く見られます。このギャップを埋めるためには、競技者は事業者に寄り添い、事業者ももっと競技者のことを理解しようとする必要があります。
eスポーツがまだ漠然とした存在だからこそ、事業者と競技者の協力が不可欠です。両者が互いを理解し合うことで、結果として新たなファン層を取り込んで、eスポーツの特別視を解消していけるでしょう。
eスポーツの選手寿命が短いのは「反射神経のせい」ではなく「業界のマネタイズ能力が低い」から
──eスポーツ業界全体の課題についてもお伺いしたく。
eスポーツ選手が早く現役を終えてしまうということです。
私は「選手寿命が20代前半で終わる」という現状に疑問を持っています。選手の能力だけを考えれば)選手としてのキャリアはもっと長く続けられるはずです。
eスポーツ選手を引退した後は、人気があればストリーマーになったり、実力を活かしてチームのマネージャーやコーチ、専門学校の講師という道がありますが、eスポーツと関係のない一般企業に就職する選手も少なくありません。
──eスポーツが早期に引退する原因は何だとお考えでしょうか?
業界全体のマネタイズ能力の低さが、早期引退の主な原因だと考えています。
例えば、30歳のeスポーツ選手が年俸3000万円を稼いでいたとして、反射神経や動体視力に多少の衰えを感じても、様々な工夫をして競技人生を続けようとするのではないでしょうか。
現状では、そのような高収入を得られるeスポーツ選手はごく少数です。
人気のある選手はストリーマーやYouTuberに転身した方が現状は稼げますし、安定した収入を望むなら早期に引退をしたほうが一般企業への転職にも有利です。しかし、eスポーツ選手としてもっと多くの人が多額の収入を得られるのであれば、例えば30歳前後まで選手として活躍し、メディア露出も増やすことで、引退後もコーチや解説者など、直結したセカンドキャリアに進む道も広がります。業界全体の成長を考えれば、その道を広げていくことが重要だと思います。
「eスポーツが当たり前になる世界」とは「“eスポーツ”というワードが消えた世界」
──貴社はMission(使命)として「eスポーツが、あたりまえにある世の中へ。」を掲げています。北浦さんがおっしゃる「eスポーツが当たり前になる世界」とは具体的にどのようなものでしょうか?
日常生活においては、公立の中学・高校の部活動にeスポーツ部が当たり前に存在し、子どもたちの選択肢の一つになっている状態です。現在は学校にeスポーツ部があると「珍しいもの」として扱われますし、公立校ではまだまだ少ないと感じます。
競技環境としては、各ゲームタイトルのプロリーグや大会が全国で開催され、市の大会から県大会、全国大会へと続くシステムが確立している状態です。家庭においては、親が子どもにeスポーツを教え、成長した子どもが親の腕前を超えるような光景が見られるでしょう。
そして、テレビ番組やネットメディアでは「eスポーツとは〜」という説明が不要になり、現在のリアルスポーツと同様に扱われる世界を、これからも私たちは目指していきます。
取材・文:小川翔太
新着の記事
- 株式会社プレイブレーン代表取締役 マイク・シタール氏 【トップインタビュー】
- ALGS札幌はアップデートできるのか──「3年連続の札幌開催が決定」Electronic Arts Esports 総合責任者 モニカ・ディンスモア【特別インタビュー】
- まずeスポーツを知ってもらうことから──市町村「33か所」と向き合う、神奈川県福祉子どもみらい局 福祉部 高齢福祉課【インタビュー】
- なぜ10年以上「eスポーツ」に関わる望月伸彦氏と筧誠一郎氏が、いま委員会を立ち上げたのか【埼玉eスポーツ推進委員会】
- eスポーツデバイスの企業に「どんな方と一緒に働きたいか」を聞いてみた【ゲーミングバザー2025編】
- テレ東・藤平氏が挑む「eスポーツの大衆化」──鍵となるのは「ゴルフ・水泳」の演出
- 【インタビュー】しーにゃさんって何者? 海外eスポーツチームで活躍する日本人コンテンツクリエイターの仕事
- eスポーツチームのスタッフってどんな仕事?
- モータースポーツがeスポーツとコラボした理由とは──株式会社日本レースプロモーション 代表取締役社長 上野禎久氏
- 小さな情報でも「集める」と価値が出る──eスポーツライター・Yossyさん