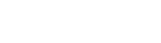ZETA千葉さんも登壇── eスポーツ・ゲームコミュニティのこれからを考える
昨今、eスポーツ業界において「コミュニティ」の存在が重要視されています。
eスポーツのコミュニティは、以下のようにいくつかのタイプに分類できます。
・ゲームタイトルのファンによるコミュニティ(例:VALORANTのファンなど)
・ゲーミングチームのファンによるコミュニティ(例:ZETA DIVISIONのファンなど)
・プロゲーマー&配信者たちのコミュニティ(例:YouTuberやTwitch配信者の界隈)
eスポーツのコミュニティは、以下のようにいくつかのタイプに分類できます。
・ゲームタイトルのファンによるコミュニティ(例:VALORANTのファンなど)
・ゲーミングチームのファンによるコミュニティ(例:ZETA DIVISIONのファンなど)
・プロゲーマー&配信者たちのコミュニティ(例:YouTuberやTwitch配信者の界隈)
ZETAインフルエンサーラウンジの様子
(東京ゲームショウ2025)
eスポーツは、まだ歴史が浅く、こうしたコミュニティづくりの方法論や運営ノウハウが確立されていません。
そこで取材班は一旦、eスポーツ業界を離れ、eスポーツよりも歴史の長い、ゲームマーケティング業界のセッションに「コミュニティ戦略」のヒントを探しに行きました。
GAME FUTURE SUMMIT 2025
「GAME FUTURE SUMMIT 2025」でコミュニティ論を学ぶ
今回の取材の舞台は、年に1度のゲーム業界のマーケターや開発者たちによる、豪華セッション「GAME FUTURE SUMMIT 2025」(2025年6月4日開催)です。
本来、最新のゲームマーケティング戦略や開発トレンドについて理解を深めるビジネスイベントですが、今回、取材班は「コミュニティ」に関するトピックスである、以下の4つのセッションに注目しました。
1.プロデューサーに聞く!SYNDUALITYのコミュニティ戦略
出演者:二見 鷹介(株式会社バンダイナムコエンターテインメント)
小島 尚也(株式会社HIKE/猿楽庁 長官)
2.広告を超える熱狂はこうつくる!逆転オセロニアとドズル社の共創コミュニティ論
出演者:香城 卓(株式会社ディー・エヌ・エー)
ドズル(株式会社ドズル)
武内 一矢(株式会社NAVICUS)
3.配信者のパワーを活かす。ゲームマーケターが知りたい事例と現実
出演者:隅田 裕也(YouTube)
脇 俊済(Side & Co.)
千葉 哲郎(GANYMEDE株式会社)
4.参加し続けたくなる“場”のつくりかた「ゲームコミュニティ」の設計と運用のコツ
出演者:速水 愛(株式会社NAVICUS)
出演者:二見 鷹介(株式会社バンダイナムコエンターテインメント)
小島 尚也(株式会社HIKE/猿楽庁 長官)
2.広告を超える熱狂はこうつくる!逆転オセロニアとドズル社の共創コミュニティ論
出演者:香城 卓(株式会社ディー・エヌ・エー)
ドズル(株式会社ドズル)
武内 一矢(株式会社NAVICUS)
3.配信者のパワーを活かす。ゲームマーケターが知りたい事例と現実
出演者:隅田 裕也(YouTube)
脇 俊済(Side & Co.)
千葉 哲郎(GANYMEDE株式会社)
4.参加し続けたくなる“場”のつくりかた「ゲームコミュニティ」の設計と運用のコツ
出演者:速水 愛(株式会社NAVICUS)
1.プロデューサーに聞く!SYNDUALITYのコミュニティ戦略
このセッションでは「ゼロからコミュニティを作る戦略」が語られました。
以下、バンダイナムコエンターテインメント 二見氏の発言
以下、バンダイナムコエンターテインメント 二見氏の発言
・オリジナルIP『SYNDUALITY Echo of Ada』は、アニメ・ホビー・ゲームが連動する新規IPとして展開された作品であり、スタート時点ではファンが存在しない状態からのスタートとなった
・いかに「最初の推し」を作るかが重要であり、コミュニティの初期熱量をどのように維持・拡大していくかがポイントになる
・定型文を用意して、Discord上でユーザーの投稿に積極的に返信した。定期的にラジオ配信を行い、ゲームの方針や開発意図について、ユーザーと共有する機会を設けた
※上記の施策により、立ち上げ時に約200人だったDiscordコミュニティは、1万人規模へと成長したとのこと
・いかに「最初の推し」を作るかが重要であり、コミュニティの初期熱量をどのように維持・拡大していくかがポイントになる
・定型文を用意して、Discord上でユーザーの投稿に積極的に返信した。定期的にラジオ配信を行い、ゲームの方針や開発意図について、ユーザーと共有する機会を設けた
※上記の施策により、立ち上げ時に約200人だったDiscordコミュニティは、1万人規模へと成長したとのこと
2.広告を超える熱狂はこうつくる!逆転オセロニアとドズル社の共創コミュニティ論
このセッションでは「ある程度育ったコミュニティをどう大きくするか」が語られました。
以下、ドズル社 ドズル氏の発言
以下、ドズル社 ドズル氏の発言
・ファンに迎合するのではなく、共通の目的を持って伴走している
・毎週配信している公開企画会議では、投稿された企画案をチームで真剣に検討し、時には厳しくフィードバックを行うことで、視聴者との信頼関係を築いている
・コミュニティの中でどうやって声を拾っていくかが今後さらに重要になる。双方向性の担保と見える化の設計がコミュニティ運営の課題である
・毎週配信している公開企画会議では、投稿された企画案をチームで真剣に検討し、時には厳しくフィードバックを行うことで、視聴者との信頼関係を築いている
・コミュニティの中でどうやって声を拾っていくかが今後さらに重要になる。双方向性の担保と見える化の設計がコミュニティ運営の課題である
以下、ディー・エヌ・エー 香城氏の発言
・『逆転オセロニア』では、リアルイベントを年間30回以上開催、開発者とユーザーが顔を合わせる場を設けることで、継続率や課金額に明確な差が表れた
・短期的な効果にとらわれず、半年〜1年後の数字に着目した評価軸が必要
・かつてはSNSのタイムラインを見るだけでユーザーの空気感が分かったが、今はグループごとに分断され、運営からは見えづらくなっている
・短期的な効果にとらわれず、半年〜1年後の数字に着目した評価軸が必要
・かつてはSNSのタイムラインを見るだけでユーザーの空気感が分かったが、今はグループごとに分断され、運営からは見えづらくなっている
3.配信者のパワーを活かす。ゲームマーケターが知りたい事例と現実
このセッションでは「インフルエンサー起用の観点のコミュニティ戦略」が語られました。
以下、YouTube 隅田氏の発言
以下、YouTube 隅田氏の発言
・配信者の仲良しグループで案件をやってもらったとしても、ファンから「案件だからやってるんだ」というのが透けて見えると、ファンは敏感になる。ファンが共感できる内容であるかどうかが成否を分ける
・(配信案件を成功させる上で)「誰かが非常に熱心であること」以上に大事なことはない。配信チームの中に誰か1人でもハマっている人がいたら、その人が中心に引っ張れる
・配信者イベントで賞金を出したとしても、賞金に関する話題は(ファンたちも)SNSで話題にしづらいが、体験や物品は後日の投稿につながりやすい。賞品を食事券にして、優勝メンバーで食事している様子を投稿することで、ファンも「おめでとう」と言いやすくなる
・(配信案件を成功させる上で)「誰かが非常に熱心であること」以上に大事なことはない。配信チームの中に誰か1人でもハマっている人がいたら、その人が中心に引っ張れる
・配信者イベントで賞金を出したとしても、賞金に関する話題は(ファンたちも)SNSで話題にしづらいが、体験や物品は後日の投稿につながりやすい。賞品を食事券にして、優勝メンバーで食事している様子を投稿することで、ファンも「おめでとう」と言いやすくなる
以下、GANYMEDE 千葉氏の発言
・配信者たちが「案件を受ける際」に重要視しているのは「自分たちの視聴者が面白がってくれるかどうか」である
・配信者個人だけでなく、その周囲にいる制作チームの存在も成果に大きく関係している。例えば、ZETA DIVISIONが手がけた『Destiny 2』のプロモーションでは、1人の制作スタッフが豊富な知識と熱量で配信を裏から支え、案件全体のクオリティを大きく押し上げた
・視聴者の記憶に残る仕掛けとして、賞金の代わりに「いらないモノ」を賞品にした。麻雀牌を模した巨大パネルを優勝者の自宅に送りつけるなど、ネタ性のある賞品のほうがSNSで話題になりやすい
・配信者個人だけでなく、その周囲にいる制作チームの存在も成果に大きく関係している。例えば、ZETA DIVISIONが手がけた『Destiny 2』のプロモーションでは、1人の制作スタッフが豊富な知識と熱量で配信を裏から支え、案件全体のクオリティを大きく押し上げた
・視聴者の記憶に残る仕掛けとして、賞金の代わりに「いらないモノ」を賞品にした。麻雀牌を模した巨大パネルを優勝者の自宅に送りつけるなど、ネタ性のある賞品のほうがSNSで話題になりやすい
4.参加し続けたくなる“場”のつくりかた「ゲームコミュニティ」の設計と運用のコツ
このセッションでは「自然と居たくなるコミュニティの条件」が語られました。
以下、株式会社NAVICUS 速水氏の発言
以下、株式会社NAVICUS 速水氏の発言
・ユーザーが「自分もこの世界の一部だ」と感じられるように、発言やアイデアが運営に拾われ、反映される仕組みが重要。「余白 → 拾う → 反映 → 広げる」の4ステップを丁寧に回すことで、発信の連鎖と成功体験が生まれる
・推しキャラの誕生日を祝う、SNSで自分の投稿が取り上げられる、イベントでファン同士が出会う──こうした感情に残る体験こそが、コミュニティへの帰属意識を育て、定着率を高める
・アップデートの背景を説明したり、寄せられた声に短くても反応することで、運営への信頼が育まれる。数字には現れにくいが、こうした誠実な対応こそが長期的な安定を支える
・単なる情報発信ではなく、双方向のやりとりが生まれる空間としてDiscordなどを活用することが鍵。「どんな関係性を育てたいか」という視点から設計することで、コミュニティは持続可能な“居場所”へと進化する
・推しキャラの誕生日を祝う、SNSで自分の投稿が取り上げられる、イベントでファン同士が出会う──こうした感情に残る体験こそが、コミュニティへの帰属意識を育て、定着率を高める
・アップデートの背景を説明したり、寄せられた声に短くても反応することで、運営への信頼が育まれる。数字には現れにくいが、こうした誠実な対応こそが長期的な安定を支える
・単なる情報発信ではなく、双方向のやりとりが生まれる空間としてDiscordなどを活用することが鍵。「どんな関係性を育てたいか」という視点から設計することで、コミュニティは持続可能な“居場所”へと進化する
GAME FUTURE SUMMIT 2025
総括
上記のセッションの内容を踏まえて「なぜeスポーツでコミュニティが必要とされるのか」を考えます。
さらにそのうえで、ゲーム業界の先進的なコミュニティ戦略が「eスポーツにどう応用できるか」を考察します。
なぜeスポーツでコミュニティが必要とされるのか
今回のセッションで感じたのは、ゲーム企業のコミュニティ作りに対する、異常な熱量です。
ゲーム関連企業が、ここまでコミュニティ作りに力を入れているのは、集客をコンテンツのクオリティだけに頼るのは「限界がある」と分かってきたからです。
どんなに面白いゲームであっても、飽きられたら人は離れます。「ゲームは面白い」が当たり前になった時代において、ゲーム自体の面白さだけで、ファンを繋ぎとめることはできません。(コンテンツ供給側の施策でファンの離脱を防げないなら)「ファン同士で繋ぎとめあってもらうしかない」という結論に至ったのでしょう。
それはeスポーツでも同じです。
どんなに人気のeスポーツでも、トレンドが終われば、プレイヤーは離れます。どんなに魅力的なインフルエンサーでも、不祥事を起こせば、スポンサーとファンは離れます。
持続可能性のあるビジネスとして成立させたい企業としては、特定のeスポーツタイトルやインフルエンサーに頼るのはリスクが高いです。
そこで、一段階、抽象度を上げた「コミュニティ」という形で管理しておくことが、リスクヘッジに繋がります。
ゲーム業界にせよ、eスポーツ業界にせよ、突破口として、面白いゲーム(eスポーツ)、面白い人物(インフルエンサー)を前面に押し出しつつも、それらの熱量を安定的にするためにも、コミュニティは必要です。
eスポーツにどう応用できるか
今回のセッションで語られた「ファンが自分ごととして関われる場をつくる」という考え方は、そのままeスポーツの現場にも応用できます。
例えば、『SYNDUALITY』の事例のように、運営がユーザーの投稿に一つずつ丁寧に応答し、透明性をもって情報発信する姿勢は、eスポーツチームの広報やSNS運用でこそ重要です。大会の告知ひとつをとっても「なぜこの選手が出場するのか」「どんな狙いがあるのか」といった背景をファンに伝えることで、運営とファンの信頼関係が深まります。
また、ドズル社とオセロニアの取り組みのように、ファンが意見を出せる場をあらかじめ設計し、その意見が実際にコンテンツに反映されるという仕組み作りにもヒントがあります。
これらは、eスポーツのイベントやグッズ開発、応援企画にも取り入れられるアイデアです。ファンをただの観客ではなく「ともにチームを運営する仲間」として扱うことで、応援の熱量も変わってきます。
さらにNAVICUSが提唱した「情緒的価値の蓄積」は、eスポーツファンの継続的な支持を得るうえで欠かせない視点です。オフラインイベントや選手との交流施策を通じて「感情が動く体験」を提供できれば、ファンの「推し続けたい」という気持ちは強化されます。例えば、「選手に会えるイベント」「SNSでの誕生日お祝いキャンペーン」「Discordでのアフタートーク」などは、すぐにでも実行できる要素です。
取材・文:小川翔太、松永華佳
新着の記事
- まずeスポーツを知ってもらうことから──市町村「33か所」と向き合う、神奈川県福祉子どもみらい局 福祉部 高齢福祉課【インタビュー】
- なぜ10年以上「eスポーツ」に関わる望月伸彦氏と筧誠一郎氏が、いま委員会を立ち上げたのか【埼玉eスポーツ推進委員会】
- eスポーツデバイスの企業に「どんな方と一緒に働きたいか」を聞いてみた【ゲーミングバザー2025編】
- テレ東・藤平氏が挑む「eスポーツの大衆化」──鍵となるのは「ゴルフ・水泳」の演出
- 【インタビュー】しーにゃさんって何者? 海外eスポーツチームで活躍する日本人コンテンツクリエイターの仕事
- eスポーツチームのスタッフってどんな仕事?
- モータースポーツがeスポーツとコラボした理由とは──株式会社日本レースプロモーション 代表取締役社長 上野禎久氏
- 小さな情報でも「集める」と価値が出る──eスポーツライター・Yossyさん
- メディア初登場!「QT DIG∞」第五人格のメンバー全員にインタビューしたら元気すぎた
- ZETA千葉さんも登壇── eスポーツ・ゲームコミュニティのこれからを考える