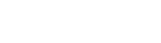なぜ10年以上「eスポーツ」に関わる望月伸彦氏と筧誠一郎氏が、いま委員会を立ち上げたのか【埼玉eスポーツ推進委員会】
普段は表に出てこない「eスポーツを盛り上げる裏方さん」にインタビューする本連載。
今回は、埼玉eスポーツ推進委員会代表の望月伸彦氏(株式会社PCCS代表取締役)と副代表の筧誠一郎氏(eスポーツコミュニケーションズ株式会社取締役会長)を取材しました。
2025年11月、同委員会は初主催となるeスポーツイベント「さいたまeスポーツコネクト」を開催。「企業eスポーツの文化を創る」のテーマのもと、eスポーツの有用性を企業に広げ、地域と企業の新たな交流の形をつくることを目的としたイベントです。
「埼玉eスポーツ推進委員会とは何か」「さいたまeスポーツコネクトとは何か」
設立や開催に至った背景や、イベントの課題・展望を伺いました。
望月 私たちの活動は「企業向けのeスポーツを盛り上げること」が原点です。いま、高校や大学のeスポーツは著しく広がっていますが、その先である企業領域には受け皿がほとんどないのが現状です。
その課題を何とかしたいという思いで、地方創生などに取り組んでいた筧さんに相談し、共同して活動を始めました。
筧 私は現在、埼玉県にある尚美学園大学で「eスポーツ概論」の講義を担当しています。また、川越市のeスポーツ協会でも理事を務めており、埼玉県とのつながりが深いことから、望月さんと共にこの取り組みを立ち上げることになりました。
今回は、埼玉eスポーツ推進委員会代表の望月伸彦氏(株式会社PCCS代表取締役)と副代表の筧誠一郎氏(eスポーツコミュニケーションズ株式会社取締役会長)を取材しました。
2025年11月、同委員会は初主催となるeスポーツイベント「さいたまeスポーツコネクト」を開催。「企業eスポーツの文化を創る」のテーマのもと、eスポーツの有用性を企業に広げ、地域と企業の新たな交流の形をつくることを目的としたイベントです。
「埼玉eスポーツ推進委員会とは何か」「さいたまeスポーツコネクトとは何か」
設立や開催に至った背景や、イベントの課題・展望を伺いました。
なぜ「10年以上」eスポーツに関わる両氏が、いま委員会を作ったのか
──お二人が埼玉eスポーツ推進委員会として活動を始めた背景について教えてください。
望月 私たちの活動は「企業向けのeスポーツを盛り上げること」が原点です。いま、高校や大学のeスポーツは著しく広がっていますが、その先である企業領域には受け皿がほとんどないのが現状です。
その課題を何とかしたいという思いで、地方創生などに取り組んでいた筧さんに相談し、共同して活動を始めました。
──筧さんが活動を引き受けた経緯を教えてください。
筧 私は現在、埼玉県にある尚美学園大学で「eスポーツ概論」の講義を担当しています。また、川越市のeスポーツ協会でも理事を務めており、埼玉県とのつながりが深いことから、望月さんと共にこの取り組みを立ち上げることになりました。
代表:望月伸彦氏
3部構成(セミナー、大会、交流会)で「企業」に刺さるイベントに
──「さいたまeスポーツコネクト」を立ち上げるにあたって、どのように工夫されたのでしょうか。
望月 今回は、セミナーとeスポーツ大会、交流会の3つを柱に据え、来場した企業の方々が「次につながる接点」を得られるよう工夫しました。単にゲームタイトルを並べて大会を開催するだけでは、他のイベントと差別化できないという課題があり、このような形を取りました。
──今後、このモデルをどのように展開していく予定ですか。
望月 まずは今回のイベントを「企業eスポーツの実例」として確立することが第一歩です。小さくても反応を得ながら改善を重ねていくことで、精度の高いモデルに育てていきたいと考えています。
私たち(株式会社PCCS)は自社でeスポーツ施設を全国に展開しています。そのため、埼玉発の成功モデルを各地の施設に横展開し「企業eスポーツの受け皿」を増やしていく構想があります。
例えば、PCCSが主催した東京ゲームショウ後の「業界交流会」も、初回はゆるやかなものだったのが、3年目には満席になるほど成長しました。「さいたまeスポーツコネクト」の交流会も、いずれ同じように多くの人が集まる場へ育っていくと感じています。
副代表:筧誠一郎
なぜeスポーツに「女性のハンデキャップ」が必要なのか
──今回の大会では『STREET FIGHTER 6(ストリートファイター6)』が採用され、女性プレイヤーにはアドバンテージ(星2つ)が設けられました。個人的にはこのルールが気になっています。ジェンダーレスであることがeスポーツの魅力だとも云われ、昨今でも男女平等を推進する風潮があるなか、このハンデキャップのルールを設けた意図を伺いたく。
筧 eスポーツは将棋や囲碁などの「マインドスポーツ」に分類されますが、男女間で勝率に差が出やすい競技なんです。実際、世界大会でも女性が上位に入るケースは稀です。
また、eスポーツ初心者の女性プレイヤーが、強い男性プレイヤーと対戦してすぐに負けてしまうと、eスポーツの楽しさを感じる前に終わってしまうことになりかねません。
今回は賞金がかからないコンテスト形式ということもあり、対戦のバランスを考慮してアドバンテージを設定しました。
──実際、女性の参加状況はいかがでしたか。
望月 今回の企業対抗戦では、全8チーム中、女性がメンバーに入っていたのは2チームのみでした。eスポーツ業界全体の傾向として、競技シーンに参加する女性の割合はまだまだ少ないのが実情です。
加えて、今回採用した『ストリートファイター6』というタイトル自体、女性プレイヤーが比較的少ないという課題があります。当初は「チームに女性を1名以上含める」という条件を検討しましたが、そうなるとチームが組めない企業も出てくるため、今回は条件として設けませんでした。
──女性参加者が増えることで、どのような効果が期待できるとお考えですか。
望月 女性が参加すると、自然と男女どちらの参加者も集まりやすくなるという実感があります。
また、今回のタイトル選定では、『ストリートファイター6』に加えて『IdentityV第五人格』の導入も検討しました。『第五人格』は女性プレイヤーも多いタイトルですが、会社内でプレイしていることを公言していないケースも少なくありません。
もし「実は、私やってます」という人が気軽に名乗り出られる場を作れれば、それだけでも大きな意義があると考えています。
企業向けイベントなのに「平日開催」ではない理由とは
──今回、競技タイトルに『ストリートファイター6』を選ばれた理由を教えてください。
望月 当初は『VALORANT』や『Apex Legends』といったタイトルも検討しました。しかし、VALORANTは5人チーム、Apexは3人チームが必要で、企業対抗戦ではメンバーを揃えるハードルが高くなります。
その点、『ストリートファイター6』は1対1で対戦が成立し、知名度も高いタイトルです。企業が気軽に参加しやすい点も踏まえ、今回の大会には最適だと判断しました。
──運営上、特に苦労された点にはどのようなものがありますか。
望月 1つ目は会場探しです。予算を抑えつつ、安定したネット回線や電源を確保できる場所を用意する必要がありました。今回は県の施設が使えたことが大きかったものの、設備面での課題には工夫が求められました。
2つ目は日程決めです。当初は平日開催の計画でしたが、アンケートを取ると平日では参加者が集まらないことがわかり、土日開催に変更しました。ただし連休の中日で、旅行で不在の人が多かったりと、集客とのバランス調整にも苦労しました。
「さいたまeスポーツコネクト」の目的とは──社員同士が社内でeスポーツの話をしやすくなること
──「さいたまeスポーツコネクト」では、「埼玉県内の企業交流」を目的の一つとされていましたが、そもそも企業内でeスポーツが浸透することでどのような効果があるとお考えですか。
望月 社内において部署や年齢を越えて人がつながる機会が広がると考えています。企業で新たに部活動を始める際、最も手軽に立ち上げやすいのがeスポーツ部です。初期費用が低く、サークル活動のような軽いノリで始められるのが特徴です。
また、eスポーツにはさまざまなジャンルがありますが、競技タイトルが違っても距離感が近く、ジャンルを越えた交流が生まれやすいという魅力があります。例えば、野球部とサッカー部が交わりにくいのとは対照的です。
こうしたeスポーツの特性を活かすことで、企業間交流はもちろん、社内のコミュニケーション活性化にもつながっていけばと思います。
──今回は企業同士の「コネクト」に焦点を当てられていましたが、学生と企業との接点づくりについて、今後お考えのことはありますか。
望月 今回のイベントには、当初大学生にも参加してもらう予定でした。しかし現状を見ると、企業側の準備がまだ十分に整っていない印象があり、企業に限定しました。
企業が「自社を知ってもらう場」として大学でイベントを開催しようとする動きは出てきています。ですが、それが成熟した仕組みとして定着するには至っていないのが実情です。
実際「社内にeスポーツ部があることで応募が増えた」という例は多いですが、企業と相性が合わず、定着しないケースもあるようです。業務が忙しくて「結局プレイできない」という声も聞きます。
今はまず、企業同士がつながり、社内で継続可能な仕組みを作ることが先決と考えています。それが整った上で、次に大学との接点を広げていけると良いですね。
さいごに、長年eスポーツに携わる両氏に「業界の変化」を訊く
──お二人は長年eスポーツ業界に携わってこられましたが、黎明期から現在にかけてどのような変化を感じていますか。
筧 私がeスポーツと関わるようになった19年前は、「eスポーツ」という言葉自体が受け入れられていませんでした。「ゲームがスポーツなわけない」と否定的に見られることも多い状況でした。
しかし、直近5年ほどで状況は大きく変わりました。高校におけるeスポーツ部が急増し、現在では全国700校以上に広がっています。およそ7校に1校がeスポーツ部を持つ時代になったとも言えます。
とはいえ、まだ課題は残っています。特に50代以上の世代では「ゲームはしょせん遊び」という疑問が根強く、価値の理解促進が次のステップだと感じています。
望月 私は2010年ごろからオンラインゲーム業界に携わっています。当時は「eスポーツ」という言葉はほとんど使われていませんでした。
そんな中、韓国に視察に行った際、eスポーツが文化として浸透し、社会に受け入れられている様子を見て「日本でもこうなれるはずだ」と思うようになりました。
やがて国内でも少しずつ変化が訪れました。例えば、池袋に「LFS esports Arena」がオープンし、2018年には日本eスポーツ連合(JeSU)が発足。この年は「eスポーツ元年」とも呼ばれ、ようやく業界の基盤が整い始めた時期でした。
──コロナ禍の影響で多くの業界に変化が訪れましたが、eスポーツ業界にはどのような変化がありましたか。
望月 国内でようやくeスポーツの土台が整いはじめたところに、コロナ禍が直撃しました。その間、自宅でできるeスポーツは広まりましたが、みんなで集まってプレイする楽しさは失われてしまいました。
ただ、eスポーツ施設の運営者たちは「いつかまた人が集まれるようになるはず」と信じて、イベント案を裏で練り続けていたんです。
その努力が今、結果として実を結び始めています。実際に、現在では多くの施設が土日に満席となる状況が生まれています。
コロナ禍は厳しい時期でしたが、各施設が次の一歩を見据える機会であったとも感じています。
筧 オフラインで集まる楽しさが本格的に広まったのは、2018年のeスポーツ元年以降のことでした。その流れが浸透しつつある中でコロナが発生し、直接会って楽しむ時間が一気に奪われました。
その会えなかったエネルギーが一斉に解放されたのが、2022年に開催された「VCT 2022 Challengers Japan Stage2 Playoff Finals」です。さいたまスーパーアリーナに2日間で約2万6,000人が集まり、コロナ禍で抑え込まれていた熱が一気に爆発した瞬間でした。
──望月さん、筧さん、ありがとうございました!
取材・文:小川翔太、松永華佳
新着の記事
- 東京eスポーツフェスタにおける東京都の「役割」とは何か ──東京都産業労働局 根岸様【インタビュー】
- 株式会社プレイブレーン代表取締役 マイク・シタール氏 【トップインタビュー】
- ALGS札幌はアップデートできるのか──「3年連続の札幌開催が決定」Electronic Arts Esports 総合責任者 モニカ・ディンスモア【特別インタビュー】
- まずeスポーツを知ってもらうことから──市町村「33か所」と向き合う、神奈川県福祉子どもみらい局 福祉部 高齢福祉課【インタビュー】
- なぜ10年以上「eスポーツ」に関わる望月伸彦氏と筧誠一郎氏が、いま委員会を立ち上げたのか【埼玉eスポーツ推進委員会】
- eスポーツデバイスの企業に「どんな方と一緒に働きたいか」を聞いてみた【ゲーミングバザー2025編】
- テレ東・藤平氏が挑む「eスポーツの大衆化」──鍵となるのは「ゴルフ・水泳」の演出
- 【インタビュー】しーにゃさんって何者? 海外eスポーツチームで活躍する日本人コンテンツクリエイターの仕事
- eスポーツチームのスタッフってどんな仕事?
- モータースポーツがeスポーツとコラボした理由とは──株式会社日本レースプロモーション 代表取締役社長 上野禎久氏