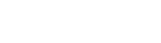テレ東・藤平氏が挑む「eスポーツの大衆化」──鍵となるのは「ゴルフ・水泳」の演出
普段は表に出てこない「eスポーツを盛り上げる裏方さん」にインタビューする本連載。
今回は、高校生eスポーツ大会「STAGE:0(以下、ステージゼロ)」の総括プロデューサー藤平晋太郎氏を取材しました。
第7回目となる今年の全国大会グランドファイナルは、大阪・関西万博(以下、万博)で開催。今回は、万博を会場に選んだ意図や背景、およびテレビ局として、eスポーツを一般層に広げるためのアプローチについて話を伺いました。
「高校生を世界に羽ばたかせたい」という(ステージゼロを立ち上げた当初から掲げている)コンセプトと親和性が高かったことが最大の理由です。ステージゼロの存在や、eスポーツに秀でた日本の高校生がいることを世界にアピールするきっかけになればと思い、万博での開催を決めました。
「ステージゼロ」は7年前にオフラインで始まりました。しかし、すぐにコロナ禍でオンライン開催に切り替わり、段階的にオフラインに戻しつつ、ようやく一昨年は東京タワー内の「RED° TOKYO TOWER」、昨年はテレビ東京の本社前広場で開催しました。
ただし、どちらの会場も多くの観客を収容できる規模ではありませんでした。今回の会場であるEXPO ホール「シャインハット」は、席数も多く、会場にフラっと立ち寄りやすい雰囲気と試合の見やすさを両立できました。
多くの方に「eスポーツを真剣に頑張っている高校生たち」の存在を知ってもらう機会になり、大きな手応えを感じています。
会場には「ステージゼロを見るために来た方々」だけでなく「万博を目的に来た方々」も立ち寄ってくださいました。むしろ、ステージゼロという大会名やeスポーツのイベントであることを知らずに来場している方も多かった印象です。
(偶然に来場してくださった方々が)高校生たちの真剣な姿を見て感動してくださる様子を目の当たりにして、私自身、とても嬉しくなりました。万博でステージゼロを開催したことで、多くの方にeスポーツの存在や真剣に頑張っている高校生たちを知ってもらうきっかけになりました。
また、「ちょっと涼みにきた」「タレントの出演情報を見て気になった」といった理由で万博会場に足を運ばれた方々が、偶然立ち寄ってくださったケースが少なくありませんでした。
そういった方々も、最後まで観戦して「面白かったね」と言ってくださいました。
今回は、高校生eスポーツ大会「STAGE:0(以下、ステージゼロ)」の総括プロデューサー藤平晋太郎氏を取材しました。
第7回目となる今年の全国大会グランドファイナルは、大阪・関西万博(以下、万博)で開催。今回は、万博を会場に選んだ意図や背景、およびテレビ局として、eスポーツを一般層に広げるためのアプローチについて話を伺いました。
高校生を世界に羽ばたかせたい──万博STAGE:0の開催意図
── まず、今回の「ステージゼロ」の開催地として、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)を選ばれた理由を教えてください。
「高校生を世界に羽ばたかせたい」という(ステージゼロを立ち上げた当初から掲げている)コンセプトと親和性が高かったことが最大の理由です。ステージゼロの存在や、eスポーツに秀でた日本の高校生がいることを世界にアピールするきっかけになればと思い、万博での開催を決めました。
「ステージゼロ」は7年前にオフラインで始まりました。しかし、すぐにコロナ禍でオンライン開催に切り替わり、段階的にオフラインに戻しつつ、ようやく一昨年は東京タワー内の「RED° TOKYO TOWER」、昨年はテレビ東京の本社前広場で開催しました。
ただし、どちらの会場も多くの観客を収容できる規模ではありませんでした。今回の会場であるEXPO ホール「シャインハット」は、席数も多く、会場にフラっと立ち寄りやすい雰囲気と試合の見やすさを両立できました。
── (取材日である)本日は大会2日目となりますが、初日を終え、万博でのステージゼロの開催にどのような手応えを感じていますか。
多くの方に「eスポーツを真剣に頑張っている高校生たち」の存在を知ってもらう機会になり、大きな手応えを感じています。
会場には「ステージゼロを見るために来た方々」だけでなく「万博を目的に来た方々」も立ち寄ってくださいました。むしろ、ステージゼロという大会名やeスポーツのイベントであることを知らずに来場している方も多かった印象です。
──万博を目的に来た方々が、偶然ステージゼロを見た時の反響で、特に印象的だったものがあれば教えてください。
(偶然に来場してくださった方々が)高校生たちの真剣な姿を見て感動してくださる様子を目の当たりにして、私自身、とても嬉しくなりました。万博でステージゼロを開催したことで、多くの方にeスポーツの存在や真剣に頑張っている高校生たちを知ってもらうきっかけになりました。
また、「ちょっと涼みにきた」「タレントの出演情報を見て気になった」といった理由で万博会場に足を運ばれた方々が、偶然立ち寄ってくださったケースが少なくありませんでした。
そういった方々も、最後まで観戦して「面白かったね」と言ってくださいました。
開催場所、EXPO ホール「シャインハット」
採用目線でスポンサーする企業も──就活でeスポーツは有利
── 今回の万博ステージゼロはメモリアルな成功を収めましたが、この成功を次に繋げていくことが、次の課題なのかと思います。今後のステージゼロの展望を教えてください。
甲子園で優勝すると、選手たちのその後の人生が変わるように、ステージゼロの結果にも同様の意義を持たせていきたいです。
高校野球では甲子園出場や優勝により、プロ野球への入団や大学進学、就職で有利になるなど、明らかに人生が変わります。ステージゼロでも、参加することの意義をしっかりと作る必要があると考えています。
── 「就職で有利になる」についてことについて詳しくお聞かせください。過去のインタビューで「ステージゼロに(学生の)リクルーティング目的でスポンサ-ドしてくれている企業が出てくるだろう」と藤平さんが予想されているのを拝見しました。今回の大会では、実際そういったお話はありましたか。
はい、実際にありました。(ステージゼロ開催)当初はゲーム系やPC、デバイス系などeスポーツに直接関連する企業がスポンサーの中心でした。
現在はeスポーツと直接的には関係のない企業が、eスポーツに取り組む高校生を「優秀な人材」として評価し、自社の知名度向上を目的に協賛してくださっています。
特に企業が(eスポーツに取り組む学生に対して)評価しているのは「コンピューターやデジタル機器に詳しい」という実用的な知見です。加えて、eスポーツ特有の戦略的思考力、分析力、状況俯瞰力、問題解決力といったソフトスキルも重視されています。
リーダーシップや反射神経なども含まれるでしょう。明確なエビデンスがあるわけではありませんが、優れた選手ほどこうした能力に長けている傾向があり、優秀な人材を獲得したい企業がスポンサーになってくださっています。
── もう少しスポンサーなどの企業とのリレーションについて教えてください。今回の万博での開催によって、(今までではありえなかった)スポンサーや業界関係者との新たなつながりが生まれましたか。
生まれました。今回、万博という大きな会場で開催したことで、ゲームパブリッシャーやメーカー、スポンサー、行政関係者など、多様な方々との接点を持てました。
実際、大阪府知事の吉村洋文氏、スポーツ庁や内閣府の方々も来場されました。府知事の吉村氏からは「大阪をeスポーツの聖地にしたい」といったお話もしていただきました。
このような、今後の発展につながるコミュニケーションが取れたのも、万博で開催したからこそでしょう。ステージゼロの認知拡大だけでなく、eスポーツ全体の発展にもつながる意義深い機会になったと感じています。
3日間の総来場者は17,897人
ステージゼロ史上最高記録を達成
「親にゲームを反対されて…」──学生eスポーツの“お決まり”を美談とする時代は終わった
── 個人的には、次回以降のステージゼロが各地のシンボリックなイベントとコラボレーションするのが楽しみです。ところで、eスポーツ大会はオンラインで開催できますが、なぜステージゼロはオフラインでの地方大会制にこだわるのでしょうか。
eスポーツはオンラインで全国一律開催も可能ですが、ステージゼロでは野球やサッカーと同様に地方大会制を採用しています。北海道、沖縄、東京それぞれに固有の苦労があり、そこにドラマが生まれて地元が応援するという、日本人に馴染み深い構造を大切にしているからです。
また、eスポーツが地方創生に役立つという視点から、地方大会を盛り上げたいという思いで協賛してくださった企業もあり、大変ありがたく思っています。
── 「各地の固有の苦労」という点において、eスポーツはリアルスポーツに比べて、練習環境の不平等さなどが生まれづらく、選手やチームのバックストーリーに感情移入しづらいという面もあるかと思います。ステージゼロでは、観客が特定のチームや選手を応援したくなるような仕掛けや演出をしていく予定なのでしょうか。
厳密には、全選手がフラットな条件で戦っているわけではないと考えています。
ゲーミングデバイスや設備などの環境の違い、コーチの有無、学校の部活動の存在など、様々な格差があります。私たちはテレビ局なので、イベントを実施して終わりではありません。大会後にドキュメンタリーとして番組化し、選手たちの舞台裏を紹介することも重要視しています。
例えば、eスポーツ部がない環境で一生懸命練習した選手や、保護者から理解を得られない中で頑張った選手など、選手やチームのバックグラウンドを丁寧に紹介することで、後からドラマ性を伝えています。
ただ、個人的には「親に反対されたけど頑張って理解してもらった」というエピソードを美談として描く時代は終わったと考えています。そうしたストーリーが必要なフェーズもありましたが、今はもう次の段階に進むべきです。
── eスポーツが次のフェーズに進んだということなんですね。参考までに貴社がこれまでに制作された大会後のeスポーツドキュメンタリーについて教えてください。
例えば、一昨年に『フォートナイト』部門で優勝した北海道江別高等学校を、後日にドキュメンタリーの取材で訪れました。
北海道江別高等学校は、北海道の大自然に囲まれた高校です。あらゆるテクノロジーを駆使するeスポーツの練習を、こんな大自然に囲まれた環境で取り組んでいるという、一見ちぐはぐな組み合わせに面白さがありました。
今後はビフォー・アフターの両方を追いかけ、イベントをやりっぱなしで終わらせず、しっかりと選手たちの裏側を紹介することで、eスポーツを盛り上げる役割を果たしたいと考えています。
ゲーム画面は情報量が多い──テレビ視聴者はどこを見ればいいか分からない
──我々、Webメディアが「狭く、深く」で情報発信をするのに対して、貴社のようなマスメディアは「広く、浅く」で情報発信されることになるかと思います。その点において、貴社がマスに向けて、eスポーツ選手の背景やドラマを伝える上で、特に意識していることは何でしょうか。
「視聴者がeスポーツの知識を持っていない」を前提に番組を作っています。
テレビ局の役割は「偶然見た人に興味を持ってもらうこと」です。
安直な例を挙げると「優勝賞金1億円」などの分かりやすい情報や「困難を乗り越えた選手のストーリー」など、視聴者が感情移入しやすい要素を示すことになります。
──「賞金額」と「選手のストーリー」が例に上がりましたが、高校生eスポーツには賞金はなく、活動期間も短いのでストーリーも希薄になりがちです。どのような演出をすべきでしょうか。
「まだ16歳なのにこんなに優秀な天才的プレイヤーがいる」というように、選手の能力の高さそのものにフォーカスすることが挙げられます。例えば、藤井聡太さんが将棋で何十手先を読めるように、eスポーツでも何十手先を数秒で読める高校生がいる可能性があります。そうした優秀な選手を見つけて紹介することがテレビの役割だと考えています。
また、進学校出身か否かなど、視聴者が感情移入できる要素も多数あります。地方ごとに異なる環境や背景を持つ高校同士の対戦では、それぞれに応援したくなるポイントが生まれます。そうした感情移入の材料を適切に提示することも重要です。
ただし、人間ドラマだけではeスポーツの真の魅力は伝わりません。今後の課題は「一瞬で驚異的なプレイが起きている」ことを伝えることです。
eスポーツ選手たちは1秒の間に状況を瞬時に分析し、高速でコマンドを入力しています。このeスポーツの競技性を、野球や陸上と同じように、わかりやすく表現する必要があります。この点においては、まだまだ演出の伸びしろがあります。
ポイントになるのは「シンプルさ」です。eスポーツに詳しい方々は細かな情報を好む一方で、より多くの方に楽しんでいただくためには、分かりやすい情報提示が大切だと考えています。
現在のeスポーツ大会の配信では、ゲーム画面に多くの情報が表示されているため、初めてご覧になる視聴者の方にとっては「どこに注目すればよいのか」が分かりにくい場合があります。
地上波での放送を想定すると、より親しみやすい形での情報提示を心がけることが、新たな視聴者層の獲得につながると考えております。
これからのeスポーツ実況──より幅広い視聴者に向けた演出の可能性
──ご指摘のとおり「シンプルな観戦UI」は現状のeスポーツ大会の弱いところです。参考までに、これまでにテレビ局が実施してきた「わかりやすい演出」によって、実際に(eスポーツのように)そこまで一般的ではなかったスポーツが、盛り上がっていった事例があれば教えていただきたいです。
ゴルフや水泳、ラグビーです。ゴルフの弾道表示、水泳のワールドレコードライン、ラグビーのルール解説など、これらの演出手法はeスポーツにも導入できます。また、チーム間の音声コミュニケーション(ボイスチャット)を視聴者に届けるなど、まだまだ演出は工夫できます。
さらに音声面に着目すると、実況・解説にも試行錯誤の余地があるでしょう。
当然のことながら、ここまでeスポーツの文化が発展してきたのは、コミュニティに愛されている現状のeスポーツキャスターの方々のおかげであるのは、言うまでもありません。
そのうえで、演出の方法論にのみ焦点を当てた話をすると、eスポーツに限らず、ルールが複雑な競技になるほど、(説明口調な)画一的な実況になる傾向があります。
これまでのリアルスポーツ観戦の歴史が証明しているように、実況者の個性や独自性により、同じ試合でも視聴体験は大きく変わる可能性があります。
例えば、かつての古舘伊知郎さんがプロレス実況で見せた(プロレスにそこまで興味のない視聴者ですらもを惹きつける)名実況が良い例です。実際、古舘さんは独自の実況スタイルで格闘技にドラマ性を持たせ(試合の内容とは無関係に)「実況自体が面白くてプロレスファンになる人」を数多く生み出しました。
繰り返しにはなりますが、並行して、将棋の藤井聡太さんのように、若くして天才的な能力を持つeスポーツ選手を発掘し、わかりやすく紹介していくことは重要です。合わせて、視聴者が感情移入できるポイントを見つけて適切に提示することも、テレビだからできることだと考えています。
──藤平さん、ありがとうございました!
取材・文:小川翔太、松永華佳
新着の記事
- ALGS札幌はアップデートできるのか──「3年連続の札幌開催が決定」Electronic Arts Esports 総合責任者 モニカ・ディンスモア【特別インタビュー】
- まずeスポーツを知ってもらうことから──市町村「33か所」と向き合う、神奈川県福祉子どもみらい局 福祉部 高齢福祉課【インタビュー】
- なぜ10年以上「eスポーツ」に関わる望月伸彦氏と筧誠一郎氏が、いま委員会を立ち上げたのか【埼玉eスポーツ推進委員会】
- eスポーツデバイスの企業に「どんな方と一緒に働きたいか」を聞いてみた【ゲーミングバザー2025編】
- テレ東・藤平氏が挑む「eスポーツの大衆化」──鍵となるのは「ゴルフ・水泳」の演出
- 【インタビュー】しーにゃさんって何者? 海外eスポーツチームで活躍する日本人コンテンツクリエイターの仕事
- eスポーツチームのスタッフってどんな仕事?
- モータースポーツがeスポーツとコラボした理由とは──株式会社日本レースプロモーション 代表取締役社長 上野禎久氏
- 小さな情報でも「集める」と価値が出る──eスポーツライター・Yossyさん
- メディア初登場!「QT DIG∞」第五人格のメンバー全員にインタビューしたら元気すぎた